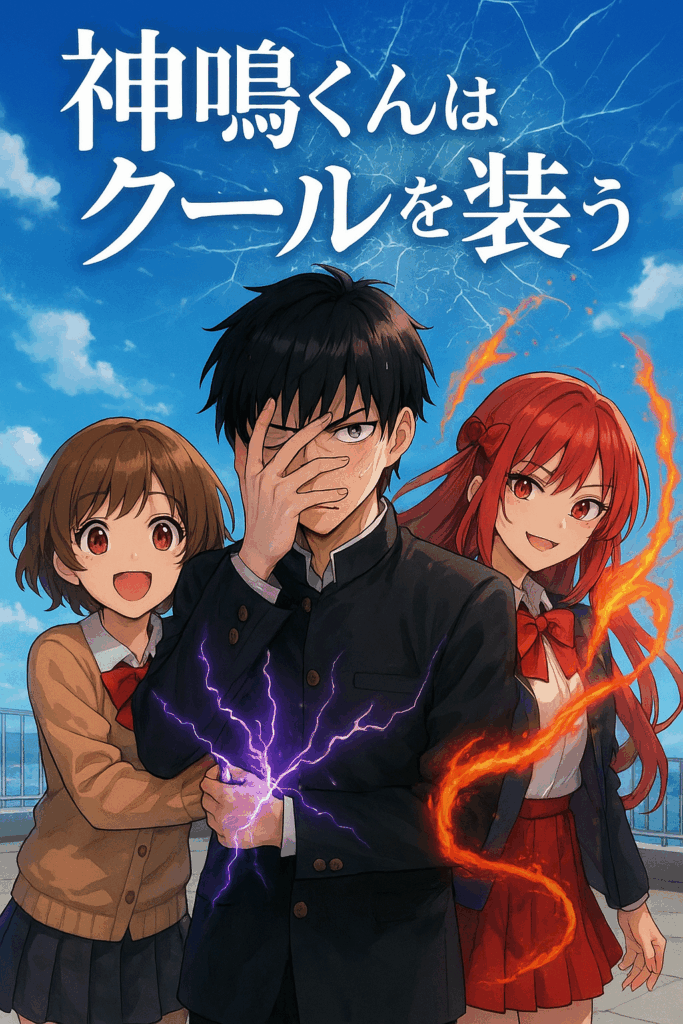目を覚ました瞬間、激しい頭痛と吐き気が俺を襲った。喉が張り付いたように乾ききっていて、全身が冷たい。ここはどこだ?
俺は冷たいコンクリートの上で跳ね起きた。六畳ほどの汚い部屋。天井にはシミがあり、カビと埃が混ざったような悪臭が鼻につく。
俺以外にも、五人の男女が、意識を失っていたかのように床に転がっていた。
「おい、アンタら! 大丈夫か!?」
俺の声に、五人は次々と意識を取り戻し始めた。彼らの表情は、俺と全く同じ、極度の混乱と怯えで満ちている。
「な、何が起こったのよ……」
30代くらいの女が、震える声で呻いた。彼女の化粧は少し崩れており、状況への不安でパニック寸前だ。
「わからん……最後に何をしていたかも、思い出せん……」
60代の男が、額を押さえながら呻いた。彼は身なりこそ粗末だが、どこか裕福そうな雰囲気を残している。
俺はすぐにドアに駆け寄り、力を込めて押し開けた。
視界に飛び込んできたのは、荒廃しきった街。窓が割れ、壁が剥がれた廃墟が延々と並んでいる。アスファルトは消え、路上は茶色い砂で覆い尽くされていた。風が吹くたびに砂塵が舞い上がる。
「うそ……だろ……」
呆然と立ち尽くす俺の後ろから、他の五人が顔を出す。彼らの息を呑む音だけが、砂風の音に混じって響いた。
「まるで、映画のセットみたいだ……」20代後半の神経質な男が、眼鏡を押し上げながら呟いた。
「何かのドッキリか? 誘拐か!?」50代の強面の男が、苛立ちを露わにして、壁を蹴った。
その時、30代の女が、ポケットから白い紙切れを取り出した。
「皆さんも、これ……」
俺は自分のポケットを探った。同じ白い紙片。広げる。
「最後の一人に、救済を」
「最後の一人……? これは、どういう意味だ?」60代の男が、恐怖に顔を歪ませる。
「救済……? 何から、救われるっていうのよ?」女の声は、泣き出しそうだった。
誰もが、目の前の光景と、この不気味なメッセージの意味を理解できずに混乱している。ここはどこだ? 何が目的なのか?
俺は壁際まで走った。コンクリートの高い壁が、この街を取り囲んでいる。外は、見渡す限りの砂漠だ。脱出は不可能。
俺たちは、この50平方キロメートルの檻に閉じ込められている。そして、この状況は、俺たち六人のうち、一人だけが生き残ることを示唆している。
極度の混乱から、一段落して、誰もが冷静さを取り戻そうと必死だった。最初に口を開いたのは、比較的冷静であろうと努めている20代後半の男だ。
「このままでは、状況は悪化する一方です。私たちは……何らかの理由で、ここに集められた。そして、生き残りを競わされている可能性が高い」
「何を当たり前のことを!」50代の男が威圧的な声を出す。「それよりも、まず誰が一番偉いか、誰が一番役に立つのか、はっきりさせるべきだろう」
誰もが自分の不安を隠すように、相手を警戒し、探りを入れている。
「いや、まずは情報共有でしょう」俺は言った。「お互い、どこの誰かも知らない。協力するにせよ、敵対するにせよ、最低限のことは知っておくべきだ」
「本名なんて明かせないわ」30代の女が、強い口調で反論した。「もしこれが、私たちを試すためのゲームなら、本名なんて、弱みになるだけよ」
「では、仮名で」20代後半の男が提案した。「職業や、過去の経験を交えながら、最低限の自己紹介をしましょう」
誰もが納得した。誰もが不安を抱えながら、相手の「正体」を探るために、しぶしぶと口を開く。
俺は立ち位置を決め、彼らの顔を見た。
「俺は、ケンだ。二十歳。これ以上は、言わない」俺はあえて若さだけを伝えた。
次に、神経質な20代後半の男が、少しお辞儀をするような仕草をした。
「僕は、ヤマモト。28歳です。元は、研究職をしていました。論理的な思考が得意です」彼は「知性」をアピールした。
「俺はゴトウだ」50代の男が、腕を組みながら威圧的に言った。「俺は昔から組織を束ねてきた。人を動かす経験は、お前らとは桁が違う」彼は「暴力と経験」をマウントに使うつもりだ。
60代のサトウは、顔を青くしながらも、自分の過去の地位に縋りついた。
「わ、私はサトウと呼んでくれ。60代だ。会社を経営していた。物資の管理や、リスクの計算なら誰にも負けん」彼は「金と経営術」を武器にした。
そして、30代の女。彼女は、目を伏せて、まるで助けを求めるように、わざと弱々しく振る舞った。
「私は……マリです、32歳。事務職しかしたことがない、何の役にも立たない女です。だから、危険なことは男性の皆さんにお願いしたいわ。皆さんの指示には従います」彼女は、「無力さ」を装って、男性陣の警戒心を解こうとしている。
最後に、30代のタケダは、怯えと不安に満ちた目で、小さな声で言った。
「俺は、タケダ。33歳だ。運送業を……やってた」
運送業。肉体労働。そして、その表情からは、極度の不安と動揺が伝わってくる。
誰もが、自分の最も優れていると思われる部分を誇示し、逆に、最も触れられたくない過去や、この場所に集められた「理由」については、徹底して口を閉ざした。
この中で、誰が最も危険で、誰が最も利用できるのか。
ゴトウが、その沈黙を破った。
「いいだろう。自己紹介は終わりだ。ならば、次は行動だ。この街は広すぎる。まずは、食料と水の有無だ。タケダ」
ゴトウは、最も怯えているタケダに、有無を言わさず命令した。
「お前は、体力があるんだろう。先行して、あの生ゴミの山を調べてこい。この街で、何が食えるか、何が使えるか、見つけてくるんだ」
タケダの顔は引きつった。生ゴミには、カラスやゴキブリ、野良犬が群がっている。危険な偵察だ。
「ゴトウさん!」ヤマモトが声を上げる。「危険すぎます! せめて二人で……」
「黙れ!」ゴトウが怒鳴った。「俺がこの場を仕切る。逆らう奴は、救済される前に、この場で処理させてもらう」
ゴトウの暴力的なマウントが、他のメンバーを黙らせた。タケダは拒否できず、絶望的な顔で、生ゴミの山の方へと向かっていった。
俺は、ゴトウの横暴を冷めた目で見つめた。この街の探索は、始まったばかりだ。
タケダが、怯えきった背中を見せながら、生ゴミの山の方へと歩き出した。ゴトウの暴力的な命令に誰も逆らえなかった。ゴトウは腕を組み、満足そうにタケダの後ろ姿を見送っている。
「ゴトウさん」
俺は、一歩踏み出し、あえて強い口調で言った。
ゴトウは苛立たしげに振り向く。
「なんだ、ケン。文句があるのか」
「文句じゃない。疑問だ」
俺は、さっきのゴトウの言葉を反芻する。ゴトウは、タケダに命令する際、こう言った。
「この街は広すぎる。まずは、食料と水の有無だ」
俺はゴトウの目をまっすぐに見つめ、指摘した。
「ゴトウさん。俺たちは全員、たった今、あの部屋で目を覚ましたばかりだ。外の状況を見たのも、全員が初めてのはずだ」
「それがどうした」
「どうして、ゴトウさんは、この街が『広すぎる』と断言できたんですか?」
俺の言葉に、周囲の空気が凍り付いた。ヤマモト、サトウ、マリの三人が、一斉にゴトウに視線を集中させる。
誰もが、この不気味な場所の「広さ」や「構造」を、俺が壁際まで走って「外は砂漠だ」と報告するまで知らなかったはずだ。だが、ゴトウは、その事実を知っていたかのように振る舞った。
ゴトウの顔が、一瞬、引きつった。彼の威圧的な態度が、ほんのわずかだが揺らぐ。
「……何が言いたい。見たままを言っただけだろうが」
「いいや、違う」マリが、すかさず口を開いた。彼女は、先ほどの「か弱い女」の仮面を外し、鋭い眼光を向けている。「ゴトウさん。この街のエリアは、約50平方キロメートル。私たちが目を覚ました部屋から外を見ただけでは、その広さまでは断言できないわ。あなたは、どこかで、その情報を得たんじゃないの?」
サトウが、動揺を抑えきれない声で付け加える。
「そうだ。ゴトウさんは、私たちよりも先に、この街にいたのではないか? それとも、このゲームの主催者側の人間なのか!」
疑心暗鬼は、一気に燃え広がった。この中で誰か一人が裏切り者、あるいは主催者側のスパイかもしれないという恐怖は、全員が抱えている。
ゴトウは顔を紅潮させ、激昂した。彼にとって、この疑惑は、せっかく暴力で掴んだリーダーシップを崩壊させる致命傷だ。
「ふざけるな! 俺がお前らみたいな雑魚の主催者なんかやってられるか! 俺だって、お前らと同じ、被害者だろうが!」
「被害者にしては、随分と余裕がありそうに見えるわよ」マリは冷ややかに言い放つ。「そして、あのタケダへの命令。あれは、誰かを先行させて、様子を見させるという、この街の隠されたルールを、あなたが知っていたからではないの?」
ヤマモトが、震えながらも、論理的に畳みかける。
「ケンさんの指摘は正しい。我々が知る情報は、この部屋と、壁と、砂漠、そして『救済』のメッセージだけ。ゴトウさんの『広すぎる』という発言は、既知の事実を前提とした表現です。説明してください、ゴトウさん。あなたが、私たちに隠している情報は何ですか?」
俺は、ゴトウと他のメンバーの間で、状況が一気に緊迫していくのを冷静に見つめていた。目的はゴトウの追放ではない。彼の持っている情報を引き出すことだ。
ゴトウは、俺たち四人の鋭い視線に囲まれ、明らかに追い詰められていた。彼は、感情的な怒りを爆発させるしかなかった。
「ちくしょう……! 知るか! 俺はただ、直感で言っただけだ! こんな廃墟が、一日で歩ききれるわけがない、と思っただけだ!」
ゴトウは怒鳴り散らし、地面に唾を吐いた。彼の言葉に、説得力はない。しかし、証拠もない。
俺は、ゴトウを追い詰めるのをやめ、一歩引いた。
「直感、ですか。わかりました。でも、次に不自然な発言があった場合、俺たちはゴトウさんの言葉を信用しない。リーダーシップは、信用の上に成り立つものだ。そうでしょう、サトウさん」
サトウは、俺に組まれたことで、いくらか安心したように頷いた。
「その通りだ、ケンさん。信用を失った人間に、この命を預けることはできない」
マリも口元を緩めた。「女性は、特に信用を重んじる生き物よ。私たちを騙そうとするなら、あなたも『最後の一人』にはなれないわ」
ゴトウは、屈辱に顔を歪ませながら、何も言い返せなかった。タケダを命令したことで一時的に得たはずの主導権は、俺のたった一つの指摘によって、あっという間に崩壊した。
そして、グループは二つに分断された。
ゴトウ:暴力と経験に頼る、今や信用を失った孤立者。 ケン、マリ、サトウ、ヤマモト:知恵と論理で結びついた、表面的な協力関係。
タケダは、そのどちらにも属さない、ただの斥候だ。
その時、遠くの生ゴミの山の方から、タケダの甲高い叫び声が聞こえてきた。
「あ、あああああああ!」
俺たち五人は、顔を見合わせた。タケダが、何かに遭遇した。
タケダの甲高い悲鳴が、砂風に乗って遠くから響いた。俺たち五人は、一瞬にして硬直する。しかし、その場で動ける人間はいなかった。誰もが、目の前で繰り広げられたゴトウへの追及で、精神的に消耗していた。
ゴトウは顔を真っ赤にしたまま、俺たち四人を睨みつけている。俺が指摘した「広すぎる」という発言の不自然さが、彼をリーダーの座から引きずり下ろした。
俺は、一歩引いて、ゴトウの言った言葉をもう一度考えた。
「ゴトウさん」俺はあえて、冷静な口調に戻した。「あなたを疑ったことは謝ります。ですが、情報を持っているなら出してほしい」
ゴトウは鼻で笑った。
「謝罪だと? 誰も謝罪なんかいらねぇんだよ、ケン。俺が『広すぎる』と言ったのは、そこに転がってる腐った標識を見ればわかるだろうが」
彼は、部屋のすぐ外に倒れている、半分砂に埋もれた巨大な案内標識を指差した。
俺たちは一斉にそちらを見た。風化して字はほとんど読めないが、その大きさは異常だ。通常の高速道路の標識の数倍はある。そして、その巨大な矢印が指し示している文字の一部が、かすかに読み取れた。
『…トリア 距離:42km』
42km。
誰もが息を呑んだ。この廃墟の街が、その外壁までの距離も含めて、最低でも数十キロメートル四方の広大なエリアを持っていることを、その標識は示していた。
ゴトウは、俺たち全員に突きつけるように言った。
「どうだ、クソガキ。お前らが寝てた間に、俺は立ち上がって、この標識を見た。こんな巨大な街が、一日や二日で端から端まで歩ききれると思うか? 見たままを、言っただけだ。それを、お前らは主催者の陰謀だの、隠された情報だのと騒ぎ立てた。お前らの『知恵』と『論理』は、その程度のもんだ」
その瞬間、俺たち四人を結びつけていた「ゴトウへの優位性」という名の連携は、脆くも崩れ去った。ゴトウは何も隠していなかった。彼はただ、目を覚ましてすぐに「生存に必要な情報」を、俺たちより早く察知し、行動に移しただけだった。
俺たちは、この異常な環境下では、過去の常識や地位が全く通用しないことを、思い知らされた。そして、ゴトウがリーダーの座を奪ったのは、単なる暴力ではなく、最も早くサバイバルの常識に切り替えたからだ。
「……くそ」俺は歯を食いしばった。
「42km……」60代のサトウが、呆然と呟いた。「都市一つ分じゃないか。しかもこの有様では、どこに水や食料が残っているか……」
マリは、一瞬の動揺を隠し、すぐに詐欺師の顔に戻った。
「ふざけてるわね。これだけの広さ、しかも砂漠に囲まれてる。私たちにまともに探せっていうの? これじゃあ、一人でなんて到底無理よ」
マリは、すぐさまゴトウに擦り寄るのではなく、チームによる協力の必然性を説き始めた。
「ゴトウさん。あなたの経験は確かに凄い。でも、あなたは今、私たち四人の信頼を失った。この街を探索し、生き残るには、あなたの体力と、サトウさんの管理能力、ヤマモトさんの分析力、そして私の交渉術。全てが必要よ。一人じゃ無理。この広大な街で、誰が一番長く生き残れるか、その生活基盤から考え直さないと」
彼女の言葉は、最も現実的だった。
ヤマモトは、眼鏡を直しながら、すぐにその現実を受け入れた。
「そうですね。この広さなら、無闇に動けば体力を消耗するだけだ。まず、私たちの生存リソースを計算し、目標地点を決める必要があります。サトウさん、元経営者としての知識で、この街の物資のありかを予測できませんか?」
サトウも、先ほどの屈辱を忘れ、頭を切り替えた。
「うむ。街の構造と、物資の残り方には、必ず法則性がある。もしこの街が、かつて鉱山か何かで栄えたなら、生活物資は中央の商業地区か、あるいは労働者宿舎の跡に残されているはずだ。最優先は水だ。水の貯水施設か、廃墟の地下室を狙うべきだ」
誰もが、自分の過去の経験を、この極限状況下での知恵として絞り出し始めた。
俺は、マリとヤマモト、サトウの三人を束ねるように言った。
「よし。ゴトウさん、タケダが帰ってくるまでは、あなたの指示に従いましょう。ただし、情報共有は絶対です。サトウさん、ヤマモトさん、タケダが戻ったら、まずあの場所から見える廃墟で、一番大きな建物の位置を確認してください。そこを当面の『拠点』候補として、物資の集約先とします」
俺は、ゴトウを完全に排除するのではなく、彼の実力を認めつつも、自分たち四人の「知性」と「協力」で牽制し、新たなバランスを作ろうとした。
その時、遠くで、再びタケダの悲鳴が聞こえた。今度は、悲鳴というよりは、何かを引きずるような音と、激しい咳が混ざっている。
タケダが、何かを見つけて、戻ってきている。あるいは、何かに追われている。
「タケダが戻ってくる!」ゴトウが叫んだ。「全員、警戒しろ! 何か、街の住人に遭遇したかもしれん!」
俺たちは、全員、一斉に生ゴミの山の方へと視線を向けた。砂塵が舞う中、タケダの姿が、かすかに見え始めた。彼の手に、何か黒いものが握られているのがわかる。そして、彼は、明らかに何かから逃げていた。
タケダの甲高い悲鳴と、何かを引きずるような音が近づいてくる。俺たちは全員、身構えた。ゴトウの「街の住人」という言葉が、俺たちの恐怖を煽る。
砂塵の向こうから、タケダの姿がはっきりと見えてきた。彼は息を切らし、激しく咳き込んでいる。逃げるように走るタケダの手には、巨大な黒いビニール袋が握られていた。
タケダは、俺たちのいる場所まで辿り着くと、その場に倒れ込み、激しい呼吸を繰り返した。
「タケダ! 何があった! 追われているのか!?」ゴトウがタケダの襟首を掴み、問いただす。
タケダは顔面蒼白で、震える指先で生ゴミの山の方を指した。
「あ、あれ……カラスだ……カラスと、野良犬が、袋を取り合ってて……。そいつらに、襲われた……」
俺たちは脱力した。タケダが逃げていたのは、この街にいる大量の動物たちだった。この街にいるのは、人間ではなく、腐臭とゴミに集まる生物たちだ。
しかし、ゴトウはタケダの掴んでいた黒い袋に注目した。
「お前のその袋の中身は何だ!?」
タケダは、その袋をまるで宝物のように抱きしめていたが、ゴトウに促され、おずおずと口を開けた。
袋の中には、濡れないように厳重にビニールに包まれた、いくつかの物体が入っていた。そして、それは、俺たちが最も求めていたものだった。
「これは……炭?」俺は、袋の中の真っ黒な塊を見て、声を上げた。
「それに、これ、着火剤だ!」ヤマモトが、興奮して前に出る。小さな缶に入ったジェル状のものだ。「誰かが使っていたのか、それともゴミとして捨てられていたのか……」
タケダは、喘ぎながら説明した。
「生ゴミの山の下……廃材と一緒に埋まってた。カラスが、しきりにこの袋を突っついてたから……中身が、大事なものだと思って……」
黒いゴミ袋に入っていたのは、水没を免れた少量の炭、固形燃料、着火剤、そして数本のライターだ。火を安定的に準備するための道具一式だった。
この発見は、俺たちに一筋の光を与えた。
「火があれば……水が作れる!」マリが、喜びで声を上げた。「この街のどこかに、雨水が溜まっているかもしれない。それを煮沸消毒すれば、飲める!」
サトウは、興奮して手を叩いた。
「そうだ! そして、食料だ! この街には、カラス、鳩、野良犬、野良猫……それに、ああ、ゴキブリも大量にいる! 煮たり、焼いたりできれば、一か八かだが、これらを非常食にできる!」
ゴトウの顔も、勝利の笑みで歪んでいた。
「よくやった、タケダ! お前のおかげで、生存の可能性が上がったぞ」
ゴトウは、タケダの肩を叩いた。彼にとって、タケダは恐怖で支配すべき駒から、今や命の恩人へと変わった。そして、ゴトウはすぐに主導権を取り戻す。
「いいか、これで生き残る基盤ができた。次は、拠点だ。ケン、お前が見つけた『一番大きな建物』を目指すぞ。火を失うな。ヤマモト、お前がその火の道具を管理しろ」
ヤマモトは頷いた。彼は火の道具を慎重に受け取り、胸元に抱きしめた。
「わかりました。水の確保を最優先にします。サトウさん、この炭の量から見て、何日分の燃料になるか、概算できますか? 無駄遣いはできません」
サトウは、すぐに経営者の顔に戻った。
「うむ。固形燃料と着火剤を最大限温存し、炭を少しずつ使えば……初期探索の移動時間を考慮して、最低でも三日間は持つはずだ。その間に、次の水と燃料を見つけねばならない」
俺たち五人の間に、一時的な「協力」と「希望」が生まれた。火という絶対的な資源が、互いの罪や疑惑を一時的に忘れさせたのだ。
しかし、俺は冷静に考えた。火は強力な武器であり、同時に強力な争いの種になる。この火の管理権を誰が持つか。そして、この火を使って、俺たちは本当に生き物を殺して食べるのか。
俺は、タケダの隣にしゃがみこみ、彼に水を少し与えながら尋ねた。
「タケダ。何にそんなに怯えていたんだ? カラスや犬に襲われただけか?」
タケダは、目をキョロキョロとさせ、震える声で囁いた。
「いや……カラスと犬だけじゃない……。あの生ゴミの山……あそこに、何かが埋まってる。俺が袋を掘り出したとき、土の下で、何か……人間に近いものが、動いた気がしたんだ……」
タケダのその言葉は、俺たちを包んでいた一瞬の希望を、再び、深い疑心暗鬼と恐怖へと引きずり戻した。
「人間? 生ゴミの中に?」ゴトウが、顔色を変えて尋ねた。
タケダは首を横に振る。「わからない。だが、この街は、俺たちだけじゃない。他にも誰かがいる。そう、強く感じたんだ……」
俺たちは、火の道具を手に入れた安堵と、この新たな恐怖に挟まれながら、とりあえず生存のための拠点を目指して、動き出すしかなかった。
タケダの「誰かが埋まっている」という言葉は、俺たち全員の背筋を凍らせた。だが、確認する術はない。そして、火という資源を手に入れた今、立ち止まるわけにはいかない。
「タケダの言うことは気にするな。興奮して見間違いをしただけだ」ゴトウが強引に結論づけた。「火の道具を最優先し、拠点に向かうぞ!」
俺たちは、サトウとヤマモトが遠望して定めた、この街でひときわ大きく見える廃墟のビルを目指して歩き始めた。荒涼とした砂の路上を、警戒しながら進む。
俺たちは、効率を上げるために、二手に分かれて探索を始めた。ゴトウとタケダが前方を警戒しながら進み、俺(ケン)とマリ、サトウ、ヤマモトが後方で火の道具を守り、周囲の建物に立ち寄りながら物資を探す。
いくつかの小さな家を覗いたが、見つかるのは、腐敗した家具、カビだらけの衣服、そして大量のゴキブリだけだった。希望はすぐに削られていく。
「こんな場所、何を探しても無駄だわ」マリが苛立ちを隠せない。「この街は、何もかもが腐りきっている」
「待て」サトウが、一つの廃屋の前で立ち止まった。「この辺りは、他の家よりも少し造りがしっかりしている。生活感が濃い。この区画は、特定の職種の人間が住んでいた場所ではないか?」
元経営者としての彼の視点は鋭かった。その廃屋は、他の家よりも窓が小さく、壁も厚い。倉庫か、作業員宿舎のようだ。
俺は躊躇なく、割れた窓から中を覗いた。中は暗く、埃が酷い。
「入るぞ。ヤマモト、火の道具は持っておけ」
俺とヤマモト、サトウ、マリの四人は、その廃屋に足を踏み入れた。悪臭がひどい。だが、腐敗臭だけでなく、微かに、乾燥した植物のような匂いが混ざっている気がした。
奥の部屋へ進むと、そこは調理場のような場所だった。錆びついた業務用コンロがあり、その横の壁には、金属製の棚が備え付けられていた。
棚の上には、数多くのネズミの糞が散乱していたが、その奥に、目を凝らすと、ネズミがかじりついた痕跡のない、いくつかの麻袋が積み重ねられているのが見えた。
「まさか……」サトウが、震える手で麻袋の一つに触れた。
俺は袋の口を掴み、一気に引き裂いた。
中から、白い粒が、埃と共に流れ落ちた。
「……米だ!」俺は思わず叫んだ。
袋は完全に密閉されてはいなかったが、砂漠の乾燥した空気と、建物の頑丈さのおかげで、中の米は、表面が少し汚れているものの、中まで腐敗してはいなかった。数カ所ネズミにかじられた穴もあったが、使える部分の方が圧倒的に多い。
「嘘でしょう、こんな物が……!」マリが駆け寄り、米粒を手のひらに載せて見た。
ヤマモトがすぐに他の袋を確認する。全部で六袋。そして、その米袋の隅に、ビニールで包まれた段ボール箱が置かれていた。
「こっちにも!これ……乾麺です!」
段ボールの中には、インスタントラーメンのような乾麺が、数十食分、丁寧にビニールで再包装されて入っていた。米と同様に、乾燥状態のおかげで、水分を吸うことなく残っていたのだ。
歓喜が、俺たち四人を包んだ。
「これで……飢えることはない!」サトウが興奮で声を震わせる。「火と水さえあれば、当面、カラスを食う必要もない!」
俺はすぐにゴトウたちに報告するために外へ出ようとしたが、マリに腕を掴まれた。
「ケン。待って!」マリの目は真剣だった。「このことは、すぐにゴトウに言うべきじゃないわ」
「なぜだ?」
「ゴトウは今、タケダの火の発見で主導権を握ったばかり。私たちがこれだけの食料を見つけたと知れば、彼はこれを独占し、私たちを自分の奴隷のように扱うわ。彼は暴力で支配しようとする人間よ。この食料は、私たち四人がゴトウに対抗し、対等な交渉をするための、唯一の武器なの」
マリの言葉は、詐欺師としての冷徹な計算に基づいていたが、この状況では理にかなっていた。ゴトウは、すぐに食料を配給制にして、自分の命令に従わない者には与えないだろう。
ヤマモトも同調する。「はい。サトウさんとマリさんの言う通り、これは私たちの生存権を守るための切り札です。ゴトウとタケダには、少量の物資しか見つからなかったと報告すべきです」
サトウは頷いた。「私も、元経営者として、資源をオープンにすることの危険性は理解している。食料は、私とマリさんで管理しよう。ケンさん、ゴトウへの報告は頼んだ」
食料という命綱を見つけた瞬間、俺たちの間の疑心と生存本能は、ゴトウの暴力支配に対抗するための秘密の同盟へと形を変えた。
俺は米と乾麺を棚の奥深くに隠し、入り口の割れた窓を、瓦礫で目立たないように塞いだ。
「わかった。俺は、何も見つからなかったと報告する。だが、この秘密は、絶対に誰にも漏らすな。もし裏切ったら、俺がお前らを、この街の生ゴミとして処分する」
俺は低い声で脅しをかけ、ゴトウとタケダの元へと走り出した。俺の心臓は、食料を見つけた喜びと、ゴトウを騙す緊張感で、激しく鳴り響いていた。
俺は、食料が隠された廃屋の窓を瓦礫で塞ぎ、ゴトウとタケダの元へ走り出した。心臓がうるさい。米と乾麺。それは、この街で生き残るための命綱だ。
ゴトウとタケダは、遠くの廃ビルの前で、不安そうに俺たちを待っていた。
「おい、ケン! 何か見つかったのか!」ゴトウが焦ったように尋ねる。
俺は、意図的にため息をついた。
「いや、駄目だ。めぼしいものは何もない。ほとんどがゴミと腐った木材だけだ。ただ、マリが、小さな缶詰を一つだけ見つけた。中身は……たぶん、ツナ缶だ。サトウさんが、皆で分ければ一食分にはなるだろうと」
俺は「小さな希望」を提示することで、ゴトウの警戒心を緩ませた。マリの言う「下手に出る」詐欺師のやり方だ。
ゴトウは舌打ちした。「ちっ。缶詰一つか。まあ、何もないよりはマシだが。くそ、この広さで本当に何もないのか」
タケダは、その「小さな缶詰」という言葉にすら、安堵の表情を見せていた。
これで、最初の嘘は通った。俺たち四人が米と乾麺という強力な秘密を共有し、ゴトウとタケダを欺いている。
俺は、マリ、サトウ、ヤマモトの顔を振り返った。
マリは、口元に薄い笑みを浮かべている。彼女の目は、「これで勝った」と確信しているようだ。サトウは、元経営者らしく、この「隠匿」という名の資源管理に、静かな満足を覚えている。ヤマモトは、不安と高揚が混じった表情で、この秘密を「論理的戦略」として受け入れていた。
俺たち四人は、この食料の秘密を共有した瞬間、口には出さないが、全員が同じ冷酷な言葉を思い出していた。
「最後の一人に、救済を」
食料は、全員を助けるためのものではない。この食料は、俺たち四人が、ゴトウとタケダという二人の協力者を、いつ、どうやって切り捨てるかを決めるための、強力な武器だ。
マリは、ゴトウとタケダに聞こえないように、俺に囁いた。
「ケン。あの缶詰は、私たち四人で分けましょう。もちろん、ゴトウとタケダには、少し多めに。彼らを働かせるための餌よ。彼らが体力を消耗して、無防備になった瞬間が……私たちのチャンスよ」
マリの提案は、すでに殺意を含んでいた。彼女は、生存競争において、躊躇なく誰かの命を切り捨てる覚悟を決めている。
ヤマモトが、理詰めで付け加える。
「あの米と乾麺は、私たち四人が自活するための時間稼ぎです。ゴトウとタケダが、私たち四人の秘密に気付かず、体力を消耗し尽くした時点で、私たちの生存率は格段に向上する。彼らを利用することが、現時点での最善の論理です」
サトウは、静かに頷いた。「経営判断だ。不要なコストは、早期に削減すべきだ。だが、今はまだ、彼らの労働力が必要だ。慎重に、そして計画的に進めよう」
俺は、口の中で砂を噛むような感覚を覚えた。俺たちの会話は、すでに『殺人計画』の立案になっている。誰もが、自分の罪の根幹にある冷酷さを、この街で呼び起こしていた。
俺は、マリとヤマモトの提案を受け入れた。
「わかった。当面、ゴトウをリーダーとして泳がせる。タケダには、引き続き危険な斥候役をさせる。火の管理は、ヤマモトとサトウさんが。食料は、マリが適当な場所に移して隠せ。俺は、ゴトウの動きを監視する」
俺たちは、表面上は協力し合う「生存グループ」を装いながら、裏では、誰を犠牲にして生き残るかという冷たい策略を始動させた。
俺たちは、この廃墟の街が、単なるサバイバルゲームではなく、断罪の場であることを、改めて理解し始めていた。
俺たちは、拠点とする廃ビルへ向かって砂の路上を進んでいた。ゴトウは先頭を歩き、暴力的な態度で「リーダー」を気取っている。タケダは、その横で怯えながらも、ツナ缶の油で少しだけ生気を取り戻した顔で、周囲を警戒していた。
俺たち四人、ケン(俺)、マリ、サトウ、ヤマモトは、彼らの数歩後ろを歩く。見た目の上では「協力」だが、俺たちの胸の内には、米と乾麺の秘密、そして冷たい計算が渦巻いていた。
このサバイバルゲームで、最初に脱落するのは誰か。答えは二つだ。
一つは、「弱い者」。体力、精神力、知恵のどれもが欠け、他の者に利用価値がないと判断された者。現時点では、怯えきったタケダがその最有力候補だ。
そしてもう一つは、「憎悪の対象」。その存在がグループの和を乱し、排除することで、他のメンバーに利益や安心感がもたらされる者。
その憎悪を一手に引き受けているのは、間違いなくゴトウだった。
彼の威圧的な態度、タケダへの冷酷な命令、そして、俺の指摘を暴力でねじ伏せようとした傲慢さ。これらはすべて、グループの協力体制を築く上で、最も邪魔な要素だった。マリの言葉が頭の中で響く。
「不要なコストは、早期に削減すべき」
ゴトウは、もはやコストではない。彼は、いつか必ずグループを裏切るリスクであり、何より、俺たち四人にとって感情的な障害だった。
マリが、俺の隣にそっと寄ってきた。彼女の視線は、ゴトウの広い背中を射抜いている。
「ケン」マリが囁いた。「あの男、いつまでもあんな態度でいられると思っているのかしら。彼は自分の暴力で、私たち全員を敵に回した。それに気づいていない」
サトウも、神経質そうに周囲を見ながら、低い声で続けた。
「彼の様な人間は、組織を管理する上では即効性があるが、危機管理においては致命的だ。彼が食料のありかを知れば、たちまち独占に走るだろう。私たちの秘密がバレる前に、彼の主導権を完全に崩す必要がある」
ヤマモトは、論理的な観点から意見を述べた。
「ゴトウさんは、現在のグループ内で最も非論理的で感情的です。私たちの生存計画にとって、最大の不安定要素と言えます。彼の排除は、戦術的に見て、優先順位が高いと考えられます」
誰もが、ゴトウを「切り捨てるべき駒」として見ていた。
だが、ゴトウを排除するとなると、彼が持つ「組織を束ねてきた」という暴力的な実力と経験、そして何より彼の体力が、俺たち四人にとって大きな脅威となる。正面からやり合えば、俺たちが勝てる保証はない。
俺は静かに指示を出した。
「正面衝突は避ける。マリ、サトウさん。この後の拠点での生活で、ゴトウが持つ火の道具の管理権を、徐々に奪う方法を考えてくれ。彼が火を失えば、タケダを支配下に置く手段もなくなる」
「わかったわ」マリが微笑んだ。「男なんて、手のひらで転がすのは慣れている。彼が一番信用している『力』を、別の形で失わせる」
ゴトウは、一歩一歩、その背中に俺たち四人からの憎悪と殺意を集めながら、拠点へと進んでいた。彼が気づいているのか、気づいていないのか。彼がこのゲームの「憎悪の対象」として、最も早い排除リストのトップに躍り出たことは、紛れもない事実だった。
俺は、再び心の中で、あの言葉を繰り返した。
「最後の一人に、救済を」
そして、俺たちの最初の策略が、静かに、そして冷酷に幕を開けた。
俺たちは、拠点とする廃ビルから数百メートル離れた場所に立っていた。ゴトウは今も「リーダー」を気取り、火の道具の管理や今後の探索ルートについて、大声で指示を出している。
「いいか、食料はツナ缶一つだ。これでは動けない。ケン、お前とタケダは、すぐに次の食料を探せ!」
ゴトウは、最も体力がある俺と、最も従順なタケダを、リスクの高い斥候に送り出そうとしていた。
俺は、この瞬間を待っていた。
「ゴトウさん、待ってください」俺は一歩前に出て、あえて低い姿勢で言った。「俺とタケダを出すのは非効率です。タケダはまだ動揺している。それに、私たち全員の安全を確保するには、まずこの街全体の構造を把握しなければならない」
ゴトウが苛立たしげに俺を睨む。「それがどうした。貴様、俺の指示に逆らうのか?」
「逆らっているのではありません。提案です」俺は続けた。「この街で一番高いのは、あの廃ビルでしょう。まずはあそこを拠点にしますが、その前に、隣の廃ビルに登って、街の全体像を把握すべきです」
俺は、数十メートル先にある、もう一つの高さのある廃墟を指差した。
「火の道具と食料がある以上、残りの四人は動くべきではありません。襲撃から守るためにも、この場に残るべきです。タケダはまだパニック寸前だ。ですが、俺とゴトウさんなら、二人だけで、短時間で登頂できます」
俺は、言葉を選んだ。
「ゴトウさん、あなたは組織を束ねる経験がある。この街の広さ、建物の配置、危険なエリアを上空から確認し、戦略を立てる。これは、あなたにしかできない、真のリーダーの仕事です。俺が、あなたの護衛をします」
俺の提案は、ゴトウの傲慢さと支配欲をくすぐるものだった。「戦略を立てる真のリーダー」という言葉が、ゴトウの自尊心を満たしたのがわかった。彼は、俺が自分にすり寄ってきた、忠実な若者だと解釈したはずだ。
ゴトウは、マリ、サトウ、ヤマモトを一瞥した。彼らは皆、無言で、ゴトウの判断を待っているように見えた。実際は、俺の提案に内心で舌打ちしつつも、これが罠の始まりであることを理解し、演技をしているのだ。
「フン。わかった」ゴトウは俺に顎を突き出した。「確かに、この街の全体像を把握するのは、俺の仕事だ。ガキ、お前が護衛しろ。他の奴らは、ここで火の道具とタケダを守っていろ。いいか、勝手な行動は許さんぞ!」
ゴトウは、誰もが「憎悪の対象」として彼を排除しようとしていることに、全く気付いていなかった。俺の提案は、彼にとっての自己肯定の機会でしかなかった。
俺たちは、すぐにその隣の廃ビルへと向かった。
ビルの中は、砂と埃がひどい。階段は崩壊しかけており、慎重に登らなければならない。ゴトウは体格はいいが、60代近く。息切れしているのがわかった。
五階まで登ったところで、俺は声をかけた。
「ゴトウさん、ここがちょうどいい。この高さなら、街の半分は見渡せます」
窓は割れており、廃墟の街並みが一望できた。無数の廃屋、生ゴミの山、そして遠くに、俺たちの拠点候補の廃ビルが見える。
ゴトウは息を整えながら、街を見下ろした。その時、俺はゴトウの死角に入り、マリから託されていたものを、素早く取り出した。
「どうだ、ゴトウさん。何か見えますか?」俺は、まだゴトウをリーダーとして扱うように声をかける。
ゴトウは、警戒心を解き、俺に背を向けたまま、腕を組んで言った。
「見ろ、ケン。この街の構造は……」
その瞬間、俺はゴトウの足元に、油を勢いよくぶちまけた。それは、タケダが見つけた着火剤だ。マリとヤマモトが、ゴトウの火の管理から、事前に抜き取っておいたものだ。
「てめぇ!」ゴトウが、足元に広がる着火剤の匂いに気づき、叫んだ。
彼は振り向いたが、もう遅い。俺は、最後の仕上げとして、小さなライターで、その油へと火を放った。
ボッ!
火は瞬時に燃え上がり、ゴトウの足元を包んだ。彼は驚愕し、バランスを崩してよろめく。床は埃と砂で滑りやすくなっている。
「ちくしょう! 貴様、何しやがる!」
ゴトウは火を避けるため、必死に後ずさった。そして、俺たちが予め崩しておいた、窓際の脆い手すりに、彼の背中が激しくぶつかった。
ガシャン!
手すりは粉砕され、ゴトウは、叫び声を上げる間もなく、そのまま五階の窓の割れ目から、下の瓦礫の山へと真っ逆さまに落下していった。
俺は、燃え盛る火と、ゴトウの落下音を背に、息を荒くした。この一連の動作は、すべて俺たち四人の綿密な計画通りだ。
マリは、ゴトウが最も信用している「力」を別の形で失わせると言った。その力とは、体力と威圧であり、それを失わせるために、俺は卑劣な裏切りを選んだ。
俺は、ゴトウの残した火の道具を拾い上げ、急いで階段を駆け下りた。
「最後の一人に、救済を」
俺は、もう二度と口に出さない、この言葉を胸に、拠点を目指して走り出した。グループから最も憎まれる者、ゴトウの排除は、完了した。
俺は五階の廃ビルから飛び出し、全速力で拠点候補の廃ビルへと戻った。手には、ゴトウが持っていた火の道具一式。
俺が、マリ、サトウ、ヤマモト、そしてタケダの待つ場所にたどり着いたとき、彼らは不安と緊張の入り混じった表情で俺を見ていた。
「ケン! ゴトウさんはどうしたの!?」マリが一番先に俺に駆け寄ってきた。その目は、心配ではなく、確認を求めていた。
俺は呼吸を整え、冷静に答えた。
「ゴトウさんは、街の構造に気を取られて、足元を滑らせた。五階の窓から……落下した」
その言葉を聞いた瞬間、タケダが崩れ落ちた。
「そ、そんな……! ゴトウさんが……」
タケダはただゴトウの威圧に屈していただけだが、彼にとってはゴトウが唯一の強大な庇護者だった。その庇護者が消えた今、彼の動揺は隠しようがない。
一方、マリ、サトウ、ヤマモトの三人の間には、一瞬の安堵と、それ以上の冷たい高揚が走った。彼らは、俺が仕掛けた裏切りが成功したことを理解したのだ。これで、憎悪の対象は消えた。
しかし、その安堵はすぐに、新たな殺意へと変わった。
ゴトウがいなくなったことで、俺たちの間にあった「殺し合いのタガ」は完全に外れた。ゴトウを排除するまで、それはあくまで「防御的」な策略だったが、今は違う。「最後の一人」になるための、純粋な攻撃に切り替わる。
そして、グループ内で最も利用価値が低く、ゴトウの派閥に属していたタケダが、次のターゲットになるのは、必然だった。
マリが、俺に耳打ちする。
「タケダはもう必要ないわ。彼はゴトウの命令で動いていた。今、彼は極度の動揺状態よ。彼が私たちの秘密を誰かに話す前に……」
マリは、言葉の代わりに、冷酷な視線をタケダに向けた。
サトウも、経営者らしく冷静に判断を下した。
「タケダくんは、心理的に脆すぎる。このままでは、食料の隠し場所に気づかれたり、私たちに不利な情報を漏らしたりするリスクが高すぎる。彼を排除することで、私たちはより安定した四人体制を確立できる」
ヤマモトは、眼鏡の奥で冷たい光を宿していた。
「論理的に、タケダさんの体力は魅力ですが、彼の精神的な不安定さは、我々の生存戦略全体のマイナス要素です。それに、五人体制よりも四人体制の方が、一人あたりの食料配分量が増えます」
俺たち三人は、言葉を交わさずとも、タケダの排除という結論で一致した。
タケダは、床に座り込み、うつろな目で周囲を見ていた。その目は、俺たちの間に流れる冷たい空気に、気づき始めていた。
「き、君たち……ゴトウさんは、本当に事故だったのか?」タケダが、震える声で尋ねた。
マリは、一瞬優しく微笑んだ。その顔が、最も恐ろしい。
「ええ、タケダさん。でも、こんな危険な街で、いつ誰が事故にあってもおかしくないわ。だからこそ、私たちで支え合わないと」
マリはそう言いながら、タケダの傍に座り込み、水を飲ませようとした。優しさという名の油断を誘っている。
俺は、マリに合図を送った。今だ。
その瞬間、俺とヤマモトが、同時に動いた。
ヤマモトは、タケダの背後から、手早く彼の首に腕を回し、窒息させる体勢に入った。
「うぐっ……!?」タケダは、何が起こったのか理解できず、もがいた。
タケダは運送業で体力があったはずだが、極度の動揺と、ヤマモトの研究職らしからぬ正確な絞め方に、抵抗する間もなかった。
サトウは、冷静に周囲を警戒している。マリは、依然としてタケダの顔の前で、心配そうに見つめる演技を続けていた。
「ごめんなさいね、タケダさん。でも、私たちも生き残らないといけないのよ。あなたは、ちょっと脆すぎるわ」マリは、心から楽しんでいるかのように、優雅な言葉でタケダに引導を渡した。
数秒後、タケダの身体は痙攣を止め、意識を失った。ヤマモトは、静かにタケダの身体を地面に横たえた。
俺たちは、たった数分で、二人を排除した。
マリが、タケダのポケットから、何かないかを確認する。
「よし。誰も見てないわ。これで、五人から三人になった」マリは、その言葉を、勝利の合図のように響かせた。
俺は、冷たい現実を突きつけた。
「違う。俺たちは今、四人だ」
マリ、サトウ、ヤマモトの三人が、一斉に俺を見た。その目は、すでに次の疑念に満ちている。
「何を言っているの、ケン。ゴトウとタケダを排除したんだから、残りは私たち四人でしょう?」マリが、警戒心を取り戻して尋ねた。
俺は、タケダの動かない身体を指差した。
「この街のルールを忘れるな。『最後の一人に、救済を』だ。ゴトウを殺した瞬間から、俺たち全員、共犯者になった。タケダを排除した今、俺たち四人の間には、明確な優位性も、明確な協力体制もない」
俺は、一歩後ずさった。
「つまり、俺たちが今からするのは、四人での協力体制の維持じゃない。三対一、あるいは二対二、あるいは全員が敵となる、新たな殺し合いの準備だ」
俺の言葉は、マリ、サトウ、ヤマモトの間の、一時的な信頼を、木っ端微塵に打ち砕いた。俺は、食料の秘密を共有するこの三人を、全員が敵として認識し直すよう仕向けたのだ。
俺たちの目の前には、タケダの遺体が横たわっている。それは、俺たちの殺意の証であり、これから始まる本物の殺し合いの、最初の犠牲者だった。
残された四人の間で、極限の緊張感が走り抜けた。
タケダの遺体が、俺たちの足元に横たわっていた。わずか数分前まで、怯えながらも生きていた人間だ。俺たち四人の間には、もはや隠しようのない殺意の残滓が漂っている。
俺は、全員が警戒し合うこの空気を、一度断ち切る必要があった。このままでは、次の殺し合いが、この場で始まってしまう。そして、それは、俺の望む形ではない。
「……落ち着け」俺は、低い声で言った。
マリ、サトウ、ヤマモトは、全員が微動だにせず、俺に警戒の目を向けている。特にマリは、タケダへの裏切りの成功に貢献したはずなのに、その目は鋭く、俺の次の行動を読もうとしていた。
「俺たちがここで殺し合ったって、誰も得しない」俺は続けた。「食料はあそこだ。火の道具はここにある。この資源を失えば、残った一人も、結局は飢え死にする」
ヤマモトが、慎重に言葉を選ぶ。
「ケンさんの言うことは、論理的です。我々は、この廃墟の街の生存可能エリアを見つけるという共通の目標を、まだ達成していません」
「そうだ」サトウが頷く。彼は、すでにタケダの遺体から視線を外し、次の戦略へと頭を切り替えていた。「この街の端、壁際まで行く必要がある。砂漠しかないのか、それとも壁の近くには別の施設や水源があるのか。情報こそが、今の私たちに残された唯一の武器だ」
俺は、まさに彼らが望む提案を口にした。
「では、そうしよう。この廃ビルを一時的な拠点候補とする。火の道具と、さっきのツナ缶はここに残す。そして、俺たち四人で、街の端を目指して探索に出る。今の俺たちに、これ以上の殺し合いの準備をする時間はない。動くことで、逆に警戒を解く」
マリは、俺の顔をじっと見つめ、俺の意図を探ろうとしていた。彼女はすぐに、この提案が「殺意を隠すための口実」であり、「移動中に裏切りを仕掛けるための機会」でもあることを察しただろう。
「いいわ、賛成よ」マリは微笑んだ。その微笑みは、油断ではなく、むしろ覚悟を示していた。「ただし、行くのは四人全員よ。誰か一人でも残れば、その者が隠された食料を独占する可能性がある」
誰もが、この提案に賛成した。誰もが、他の誰かの裏切りを警戒し、誰もが、裏切りの機会を求めていたからだ。
俺たちは、再び荒涼とした街を歩き始めた。目指すは、見渡す限り続く砂漠の壁、その一番近くの廃屋群だ。
四人の間隔は、絶妙に不自然だ。誰もが、いつでも動ける距離を保ちながら、同時に、誰か一人が襲われたときに、助けに入れない距離を維持している。
俺は、一歩前に出る。すぐに、ヤマモトが、俺の斜め後ろに位置取った。彼は、俺の背後から襲いかかることを最も容易にするポジションを選んだのだ。
「ヤマモト」俺は声をかけた。「そんな近くにいると、砂塵で目がやられるぞ」
「いえ、大丈夫です、ケンさん。私は、皆さんの周囲の警戒をしています」ヤマモトは冷静に答えたが、その声には、微かな殺意が混じっていた。
俺は、警戒をマリとサトウに向ける。
マリは、サトウの隣にいる。マリは、サトウの弱さを利用して、彼を盾にするつもりだろう。そしてサトウも、マリの冷徹な計算力を、一時的な庇護として利用している。
三人(マリ、サトウ、ヤマモト)対 一人(俺)。
この構図は、タケダ排除の瞬間から、既に固まっていた。マリの知恵、サトウの経営的な判断、ヤマモトの論理的な実行力。彼らが組めば、俺を排除することは容易だと考えているはずだ。
歩き始めて、十数分。俺たちは、特に荒廃した住宅街の路地に入り込んだ。
その瞬間、攻防が始まった。
「ケン、後ろ!」マリが突然、大声で叫んだ。
マリの視線は俺の背後ではなく、俺の足元を指していた。
反射的に足元を見ると、路地の影から、巨大な野良犬が唸り声を上げて飛び出してきた。ゴトウを排除する際にも、彼らが発見したと言った、この街に大量にいる危険な動物だ。
俺はとっさに身を翻し、犬の牙を避けた。
「くそっ!」
その時、マリが叫んだのは野良犬の存在ではない。それは、合図だった。
俺が野良犬に気を取られた瞬間、ヤマモトが背後から、硬い瓦礫の塊を俺の頭めがけて投げつけてきた。
ガッ!という鈍い音。瓦礫は俺の頭をわずかに掠めたが、直撃は免れた。
「裏切り者!」俺は叫び、野良犬とヤマモト、二つの脅威に挟まれた。
マリは、サトウの腕を掴み、彼を俺と野良犬の間に押し出すように誘導した。
「サトウさん! 野良犬を食料にするチャンスよ! 撃退して!」
サトウは悲鳴を上げた。「やめろ! マリ!」
マリは、サトウを野良犬への囮にし、俺の動きを封じようとしたのだ。
三人対一の攻防は、野良犬という第三者を巻き込み、卑劣な形で始まった。俺は、まずどちらの敵を排除すべきか、瞬時に判断しなければならなかった。俺の脳裏には、「最後の一人に、救済を」という言葉と共に、俺自身の罪の根幹にある冷酷さが甦っていた。
マリの裏切りを合図に、攻防は一瞬で地獄と化した。
野良犬が唸り声を上げて俺に飛びかかってくる。同時に、ヤマモトが投げつけた瓦礫が、耳元を掠めていった。そして何より卑劣だったのは、マリがサトウを盾として、野良犬の前に押し出したことだ。
「サトウさん! 野良犬を食料にするチャンスよ! 撃退して!」マリの甲高い声が響く。彼女は、サトウの恐怖を利用して、俺の動きを封じようとしている。
「やめろ! マリ!」サトウの悲鳴が路地に響く。野良犬は、目の前に現れたサトウの怯えた姿に標的を変え、その足首に牙を剥いた。
状況は最悪だ。
野良犬を相手にすれば、ヤマモトとマリの連携攻撃を受ける。ヤマモトは頭脳派だが、瓦礫を正確に投げる実行力がある。マリは狡猾で、サトウを囮にした。
俺は瞬時に判断した。一番の脅威は、野良犬でも、サトウでもない。冷静に状況を操り、俺の命を狙っているヤマモトとマリの連携だ。
「サトウさん、伏せろ!」俺は全力で叫んだ。
サトウがパニックのあまり、反射的に地面にうずくまった。野良犬の牙は、サトウの頭上を通過する。
その一瞬の隙に、俺は野良犬に向かって走った。サトウを助けるためではない。野良犬を利用するためだ。
俺は野良犬の横をすり抜け、瓦礫で汚れた腕を、そのままヤマモトがいた方向へ振り抜いた。
「てめえ!」
俺の拳は、ヤマモトの顔面を捉えた。ヤマモトは眼鏡を吹き飛ばされ、呻きながら壁に激突した。彼は、俺がサトウと野良犬の相手をしている間に、冷静に次の攻撃を準備するつもりだったはずだ。予想外の反撃に、彼の論理的思考は一瞬で崩れた。
「ヤマモト!」マリが叫び、動揺した。
その隙を見逃さず、俺はヤマモトの近くに落ちていた鉄パイプの残骸を拾い上げた。
同時に、背後から野良犬が再び俺に飛びかかってくる。
「グアァ!」
「マリ!」サトウが、野良犬の攻撃を避けて、悲鳴を上げながら立ち上がった。野良犬は再びターゲットをサトウに向け、彼の腕に食らいつこうとする。
「クソ!」
俺は、ヤマモトを追い詰めるのを止め、野良犬に鉄パイプを叩きつけた。
ガン!
野良犬はけたたましい鳴き声を上げ、足を折られたようにキャンキャン吠えながら、路地の奥へと逃げ去った。
俺は鉄パイプを握りしめたまま、残りの二人に振り向いた。
ヤマモトは眼鏡を失い、顔面を抑えてうずくまっている。彼は今、知性という武器を失い、最も無力な状態だ。
マリは、サトウを盾にしようとして失敗し、完全に孤立していた。彼女の顔からは、先ほどの優雅な笑みが消え、恐怖が浮かんでいる。
そしてサトウ。彼は腕を擦りむいただけで済んだが、俺が自分を助け、マリが自分を囮にしたという事実に、完全にパニックに陥っていた。
「マ、マリさん……なんで……俺を……」サトウはマリを指差し、怒りと恐怖で声が震えている。
「サトウさん、落ち着いて!あれはケンが野良犬を誘導したのよ!私はあなたを……」マリは必死に言い訳をしようとする。
俺は鉄パイプの先端を、ヤマモトの首筋に向けた。
「嘘をつくな、マリ。あんたがサトウさんを盾にしたのは、俺たち全員が見ていた。そして、ヤマモト。あんたの論理的な計算は、俺の拳で狂ったようだな」
俺は、一気にこの場の主導権を取り返した。ゴトウを排除したことで生まれた殺し合いのタガは、今、俺の力によって、一時的に制御された。
この瞬間、三対一の構図は崩壊した。
俺は、鉄パイプを地面に突き刺した。そして、サトウに静かに言った。
「サトウさん。ゴトウを排除したのは、私たち四人の合意だ。だが、あんたを野良犬の餌にしようとしたのは、マリだ。この街で誰を信用するか、自分で決めろ」
サトウは、俺とマリを交互に見つめる。彼の表情は、すでにマリへの憎悪に満ちていた。
「最後の一人に、救済を」。
俺は、知っている。このサバイバルで最も危険なのは、マリのような計算高い裏切り者だ。そして、サトウは、今やマリを排除するための、最も感情的な武器になる。
俺は、次のターゲットを、静かにマリに定めた。
俺の言葉が、サトウの心に火をつけた。彼の目は、自分を囮にしたマリへの憎悪で、らんらんと輝いている。
マリは、サトウが自分を裏切り、俺に味方する決断を下したことを瞬時に察した。彼女の顔は、これまでの冷静な詐欺師の仮面を剥がされ、醜い恐怖に歪んでいた。
「くそっ……!」
マリは、羞恥心も外聞もかなぐり捨てた。彼女は、俺たち三人に背を向け、絶叫にも似た悲鳴を上げながら、路地の奥へと走り出した。
「待て、マリ!」サトウが叫ぶ。その声には、追いついて彼女を罰したいという感情が込められていた。
俺は、マリが逃げ出すのを、黙って見送った。鉄パイプを握る手に力を込める。
マリはいつでも殺せる。
彼女は、食料の隠し場所を知っているというアドバンテージを失い、武器もない。単独で逃げ出したマリは、この広大な廃墟の中で、ただの怯えた獲物に過ぎない。飢えか、野良犬か、あるいはまた別の何かに、いずれ処理されるだろう。
それよりも、俺の目の前に残っている二人の処理が優先だ。
俺は、走り去るマリではなく、うずくまるヤマモトと、憎悪に燃えるサトウに意識を集中した。
ヤマモトは、眼鏡を失い、頭を抑えたまま動けない。彼は論理的な判断を奪われ、今やグループ内で最も無力な「弱者」だ。
サトウは、マリへの怒りで興奮状態にあるが、体力も戦闘能力も低い。しかし、この怒りは、俺にとって利用価値のある爆薬だ。
俺の脳裏で、冷たい計算が働いた。
ヤマモト:負傷しており、いつでも処分できる。しかし、彼の知性はまだ利用できるかもしれない。
サトウ:感情的になっており、俺の指示に従う可能性が高い。彼にマリを追わせれば、俺は彼らの両方を消耗させられる。
「追うな、サトウさん」 俺は静かに命じた。
サトウは立ち止まり、俺を振り返った。
「な、なんでだ、ケン! あいつは俺を殺そうとしたんだぞ! このまま逃がして……」
「わかっています」俺は言った。「ですが、彼女はもう脅威じゃない。体力を無駄にするな。それよりも、今、一番危険なのは誰か、考えろ」
俺は、鉄パイプを握りしめ、うずくまるヤマモトを指差した。
「マリは逃げた。だが、ヤマモトはここにいる。彼は、俺たち全員の秘密、特に食料の隠し場所を知っている。そして、俺の顔と、俺がゴトウを殺した瞬間を、覚えている」
サトウの顔から、マリへの怒りが薄れ、代わりにヤマモトへの恐怖が浮かんだ。そうだ、マリは遠くへ行ったが、ヤマモトは、秘密を握ったまま、すぐそこにいる。
俺はヤマモトに近づいた。彼は、視線を合わせようとしない。
「ヤマモト。あんたの論理は、俺たちが先に動くことを推奨した。その結果がこれだ。あんたの知性は、もはや俺たちを助けるツールではない。危険因子だ」
ヤマモトは、震える声で懇願した。
「待ってくれ、ケンさん……! 僕は、協力する。食料の配分管理、街の探索ルート……僕は、まだ役に立てる! 殺さないでくれ!」
俺は、鉄パイプを振り上げ、ヤマモトの頭上に掲げた。
「サトウさん」俺は、鉄パイプ越しにサトウに視線を送り、冷酷な目で囁いた。「この街のルールを忘れるな。弱者と、憎悪の対象。そして、利用価値のない情報源は、即座に排除される。あんたは、どうする」
サトウの顔は、恐怖と、再びの生存本能でぐちゃぐちゃになっていた。彼は、今、俺に逆らえば、自分がヤマモトの隣に並ぶことを理解している。そして、ヤマモトを排除すれば、食料は俺と彼、そして逃げたマリの三人で分け合うことになる。
「……ヤマモトくん」サトウは、うめくように言った。「すまないが……君は、あまりに不安定だ。私たちは生き残らなければならないんだ」
サトウは、自らの手で、ヤマモトを排除する意思を示した。俺の策略は成功した。
俺は、鉄パイプを静かに下ろした。
「待て。サトウさん、手は汚すな」俺は言った。
俺は、ヤマモトの抵抗を許さぬよう、彼の腹部に強烈な蹴りを入れた。ヤマモトは呻き声を上げて倒れ伏す。
「マリを追うのは、その後だ。まずは、この街の端を見つける。情報だ、サトウさん。あんたの言った通りだ」
俺は、倒れたヤマモトの身体を見下ろした。いつでも殺せる。だが、彼の知識は、俺がマリと戦う上で、最後の切り札になるかもしれない。
俺は、ヤマモトを気絶させるだけに留め、サトウと共に、再び街の端を目指して歩き始めた。サトウは、俺の隣で、自分の手が血に染まらなかったことに安堵しつつ、マリへの怒りを燻らせている。
この時点で、俺は二人を手の内に入れた。残りはマリ。俺の「最後の一人」への道は、まだ続く。
俺は、意識を失ったヤマモトを路地の影に横たえ、サトウと共に再び歩き始めた。サトウはマリへの憎悪で頭が一杯だ。
「ケンさん、マリを追わないんですか!? あいつは必ず、食料の隠し場所に戻るぞ!」サトウが焦れたように言った。
「落ち着いてください、サトウさん」俺は冷静に答える。「マリはもう、食料の場所に戻るほどの勇気はない。彼女は逃げた。野良犬か、飢えが彼女を処理するのを待つだけでいい。それよりも、俺たちの目の前の敵を優先するべきだ」
俺はあえてそう言ったが、心の中では、マリの排除が急務だと理解していた。
マリは、俺たちが米と乾麺を見つけた隠し場所を正確に知っている。そして、俺がゴトウとタケダを排除したことで、彼女は俺の冷酷さを理解した。彼女が食料を独占し、新たな協力者を見つける前に、俺が彼女を仕留めなければならない。
俺は、サトウの顔を覗き込んだ。
「サトウさん。あんたの言いたいことはわかる。マリを放置するのは危険だ。では、先にマリを倒す。それでどうです? 食料の秘密を知る裏切り者は、全員排除する。ヤマモトは動けない。残るはマリだ」
サトウの顔が、期待と安堵で輝いた。「そ、そうか! ケンさんがそう言ってくれるなら、心強い! マリさえいなくなれば、我々二人の勝ちだ!」
二人の勝ち。
俺はサトウのこの言葉を心の中で嘲笑った。サトウはマリへの復讐心と、俺への依存心で、自分が俺の次の排除リストの二番目にいることに気づいていない。
「では、あの廃ビルの方へ戻りましょう。マリは、必ずあの辺りを徘徊しているはずだ」
俺は、警戒を怠らず、サトウと共に廃墟の中を移動した。俺は、サトウの動きを常に視界に入れ、彼がいつでも俺に攻撃を仕掛けられない距離を保つように注意を払っていた。
マリは、俺がゴトウにしたように、俺の死角から不意打ちを仕掛けてくるだろう。だが、俺は鉄パイプを握りしめ、常に背後を警戒している。
路地を曲がり、瓦礫が堆積した広い空間に出た。
「マリ! いるなら出てこい! 無駄な体力を使うな!」俺は敢えて大声で叫んだ。これは、マリを誘い出すための罠だ。
「ケンさん、後ろは……」
サトウの声が、異常に近かった。
俺は反射的に振り向いたが、もう遅い。
ゴトウ、タケダ、ヤマモトを排除し、俺が優位に立ったと慢心していた、その一瞬の隙。
「すまない、ケンさん」
サトウが、絶叫にも似た謝罪を口にした瞬間、俺の視界は、閃光に包まれた。
ゴトウを殴りつけるために使った、あの鉄パイプ。それが、俺の頭部に、凄まじい勢いで叩きつけられたのだ。
俺の全身から力が抜け、鉄パイプと頭蓋骨がぶつかった鈍い衝撃音だけが、世界を満たした。激しい頭痛と、意識が遠ざかる感覚。
俺は、そのまま前のめりに倒れ込んだ。
裏切り。
俺が警戒すべきは、逃げたマリでも、無力なヤマモトでもなく、最も頼りにしてきたサトウだった。
薄れゆく視界の中で、俺の顔のすぐ隣に、マリの顔が見えた。彼女は、先ほどの恐怖の表情ではなく、冷酷な笑みを浮かべていた。
「バカな男ね、ケン」マリの声が、遠くで聞こえる。「あなたは、私が弱い女を演じたことしか見ていなかった。そして、サトウさんが私を裏切ったと思った?」
マリは、倒れた俺の鉄パイプを拾い上げ、サトウに渡した。
「サトウさんと私は、あなたがゴトウを排除するずっと前から、協力関係にあったのよ。サトウさんの『元経営者』の肩書きは嘘。彼はただのサクラ。私に、論理的な言い訳と隠蔽の協力をする役割だった」
マリの真実の言葉が、俺の脳裏を貫いた。サトウは、最初からマリと組んでいた。マリが「か弱い女」を演じ、サトウが「管理能力」をアピールしたのも、すべては俺たちを欺くための役割分担だったのだ。
俺がゴトウへの追及を仕掛けた時、マリがすぐに乗ってきたのも、俺たち四人を「協力体制」という形で、彼女の掌で踊らせるためだった。
そして、俺を裏切ったように見せかけた、あの野良犬の攻防。
「あの時、私がサトウさんを盾にしたように見えた? 違うわ。あれは、サトウさんが私に近づく俺の警戒心を解くための、私たち二人の芝居よ。そして、あなたが私を助け、サトウさんへの信頼を失うよう仕向けたの」
マリは俺を見下ろし、勝利を確信した声で言った。
「あなたは、暴力と裏切りで支配しようとした。でも、私は信頼の構築と、心理的な操作で支配したのよ。最後の一人になるのは、私よ、ケン」
俺の意識は、暗闇に飲み込まれていった。ゴトウを排除し、タケダを殺し、ヤマモトを無力化した俺の冷酷な戦略は、最も危険な裏切り者、マリの用意した筋書きの中で踊らされた、滑稽な道化師の結末だった。
俺の意識は、暗闇に飲み込まれていく。頭部に叩きつけられた鉄パイプの衝撃が、全身の感覚を奪っていた。
薄れゆく視界の中で、マリの冷酷な笑みが、俺の顔のすぐ隣にあった。彼女は勝利を確信している。
「あなたは、暴力と裏切りで支配しようとした。でも、私は信頼の構築と、心理的な操作で支配したのよ。最後の一人になるのは、私よ、ケン」
その横に立つサトウが、鉄パイプを握りしめている。彼は元経営者としての仮面を剥がされ、その顔は、マリへの絶対的な服従と、何かに怯えるような安堵で入り混じっていた。
「サトウさん……あんたも……」俺は、かろうじて掠れた声を出した。
マリは、俺の最後の問いかけを、憐れむように受け止めた。彼女は、サトウの隣に立ち、親愛の情を示すように、彼の腕にそっと手を添えた。
「サトウさんの目的はね、ケン。彼が長年経営者として失ってきた、もっとも甘くて、もっとも愚かなものよ」
マリは、冷たい目でサトウを見つめながら、その真実を暴いた。
「サトウさんはね、私の愛が欲しかったの。彼は、この街で生き残ることで、私という若くて美しい女性の隣に立つ、ただ一人の男になりたかった。彼の過去の地位や金じゃ買えなかった、絶対的な愛情を、この極限状況下で手に入れようとしたのよ」
サトウの顔が、一気に赤く染まった。羞恥、そしてマリにすべてを暴かれた絶望。だが、彼の瞳は、それでもマリへの執着を捨てていない。
「マリさん……俺は、俺は君のためなら……!」サトウは、マリの手に頬を擦り寄せようとした。
マリは、さっと手を引き、冷笑した。
「バカね。彼の管理欲も、彼の愛情も、私にとってはただのツールよ。彼は、ゴトウやあなたのような危険な牡馬を排除し、私に絶対的な安全と食料の管理をもたらすための、忠実な老犬に過ぎないわ」
「そう、サトウさん。あなたの目的は達成されたわ。あなたは、私という『資源』の隣に立つことを許された。ただし、私の支配下でね」
サトウは、その残酷な言葉に打ちのめされながらも、マリに一言も反論できない。彼は、愛という名の鎖で、マリに完全に支配されていた。
俺の意識は、遠のいていく。
ゴトウは暴力に溺れ、タケダは恐怖に怯え、ヤマモトは知性に固執し、そしてサトウは愛という幻想に縋った。そして、俺は、傲慢と裏切りに酔いしれた。
この街で、最も危険なのは、他人の欲望を利用する人間だ。
マリは、俺たち全員の罪と弱さを、自分の生存のための完璧な筋書きに組み込んでいた。
「最後の一人に、救済を」。
その救済は、マリに与えられるだろう。彼女は、愛という最も美しい嘘で、この断罪の街を制圧したのだ。俺の視界は、ついに暗闇に閉ざされた。
ケンは、倒れたまま動かなくなった。彼の若くて傲慢な目が、光を失っていくのをマリは確認した。
マリは鉄パイプを瓦礫の上に置き、サトウを振り返った。勝利の陶酔感が全身を巡る。ゴトウ、タケダ、ケン。最も危険な男たちを、彼女はすべて愛という名のロープで縛り、排除させた。残るは無力なヤマモトと、この忠実な老犬、サトウだけだ。
「さあ、サトウさん。終わったわ」マリは優雅に微笑んだ。「これで、私たちの計画通りよ。食料を確保し、ヤマモトを利用すれば、この街は私たち二人のもの。あなたは、私に最高の安全性をもたらしてくれたわ」
サトウは、俺たちに背を向け、ケンを殴りつけた鉄パイプを静かに地面に置いた。彼は、汚れた手で、マリの顔にそっと触れようとした。
「ああ、マリさん。すべては君のためだ」サトウの声は、かすれ、そして異常に熱を帯びていた。「私は、君にふさわしい唯一の男になった。ゴトウもケンも、君の価値を理解できなかった。だが、私だけは、君の純粋さと美しさを、この汚れた世界から守り抜いた」
マリは、一瞬たじろいだ。彼の言葉は、彼女が仕組んだ「愛の幻想」を、遥かに超える倒錯的な熱量を帯びていた。
「ええ、サトウさん。ありがとう」マリは距離を取り、あくまで支配者として話した。「では、早くここを離れましょう。ケンやタケダの遺体は、すぐにカラスの餌になるわ。食料の隠し場所に戻って……」
その時、サトウがマリの腕を力任せに掴んだ。
「待て、マリ」
彼の握力は、元経営者とはかけ離れた、強い狂気に満ちていた。マリは、今まで欺いてきた相手と同じレベルだと油断していたが、このサトウは、ゴトウやケンとは全く異なる、本物の倒錯者だった。
「何を、サトウさん……」
サトウは、マリを逃がさないように掴んだまま、マリの頬に顔を近づけた。彼の目は、獲物を前にした飢えた獣のように、ぎらついていた。
「もう終わりだ、マリ。私の献身的な愛によって、すべてが終わったんだ」
「私たち二人が生き残る。それは、マリ、君のすべてが、私のものになるということだ」サトウの顔が歪む。
「君の肌も、髪も、その冷酷な頭脳すらも、私という唯一の庇護者がいなければ、一瞬でゴミになる。マリ、君のその美しい爪の先まで、すべてが私の所有物になる。君はもう、私に嘘をついたり、私を支配しようとしたりする必要はないんだよ」
マリの背中に、冷たい汗が流れた。彼女は、愛を演じた。だが、サトウは、その演技を真実として捉え、彼女の存在すべてを自分の理想の所有物として完成させようとしていたのだ。
彼女がゴトウやケンに抱いた警戒心よりも、遥かに恐ろしいものが、この老人の胸の中にあった。彼は、彼女の肉体的な愛だけでなく、彼女の自由意志そのものを、永遠に奪おうとしている。
「サトウさん、何を言ってるの。私たちは対等なパートナーよ。冷静になりなさい!」マリは、いつもの支配的な口調で彼を宥めようとした。
しかし、サトウは微動だにしない。
「対等? マリ、君はまだ、私に嘘をつこうとしているのか? 君は私の『理想の妻』だ。妻と夫は対等ではない。妻は夫の庇護を受け、夫に従う。私の手によって、君の純粋さは守られたんだ。これからは、私がお前を管理する。食料だけでなく、お前の呼吸、お前の行動、すべてをだ」
サトウの顔には、恍惚とした支配欲が浮かんでいた。彼にとって、このサバイバルは、彼女を完璧な所有物にするための、結婚の儀式だったのだ。
マリは、自分の武器が、完全にサトウによって奪い取られたことを悟った。彼女が彼に与えた「愛」は、彼にとって永久的な支配権の証書になってしまった。
「最後の一人に、救済を」。
その救済は、マリにとって、永遠の奴隷となることだった。彼女の冷酷な知性は、このサトウの倒錯した愛という、最も非論理的で予測不可能な脅威の前で、完全に凍り付いた。
マリの顔から、一瞬で血の気が引いた。彼女が仕組んだ「愛の幻想」が、彼女自身の命を脅かす狂気の鎖となったことを悟ったのだ。
「サトウさん、正気に戻って! 私たちには、まだ食料があるわ。ヤマモトも生かしておく必要がある。私を殺したら、あなたは孤独になり、すぐに飢え死にするのよ!」マリは必死に理性を訴えかけた。
しかし、サトウの倒錯した支配欲は、理性などでは止められなかった。
「違う、マリ。私は君を殺さない。私の理想は、君の自由な意志を永遠に停止させることだ」
サトウは、マリを掴んだ腕にさらに力を込めた。彼の顔は、愛と狂気の混ざった歪んだ表情をしていた。
「私に従わないマリは、欠陥品だ。だが、死んだ君は、永遠に私の所有物として、美しいままでいられる。君の魂は、この街で永遠に私に縛られるんだ!」
サトウは、狂気に満ちた眼差しで、瓦礫の上に落ちていた鉄パイプに手を伸ばした。
マリは、これが最後の瞬間だと悟った。彼女の計算は、すべてこの男の病的な執着によって崩壊した。
「ふざけないで!」
マリは、か弱さを装うことをやめた。彼女は本能的な抵抗を開始した。腕を掴むサトウの手を、爪を立てて全力で引っ掻いた。サトウの老いた皮膚が破れ、鮮血が滲む。
「ぐっ!」サトウが怯んだ一瞬、マリは鉄パイプを掴もうとする彼の手を避け、地面に転がっていた鋭利なガラス片を素早く掴み取った。
サトウは怒鳴った。「裏切り者め! 永遠に私のものになれ!」
サトウは鉄パイプを振り上げ、マリの頭部めがけて振り下ろそうとした。マリは身をよじってそれを避け、鉄パイプは瓦礫に激しい音を立てて叩きつけられた。
その隙に、マリは獣のような目でサトウに飛びついた。彼女は、彼の首元ではなく、彼の腹部の柔らかい皮膚に、手にしたガラス片を躊躇なく突き立てた。
ズブッ!
ガラス片が、サトウの腹部に深く食い込んだ。サトウは苦悶の表情を浮かべ、喉の奥から呻き声を上げた。
「マ、マリ……! お前……」
サトウの力は急激に失われ、マリを掴んでいた手も緩んだ。しかし、死の直前の本能的な力は、驚くほど強かった。
サトウは、ガラス片が刺さった腹部を気にせず、手にしていた鉄パイプを最後の力で、マリの胸元に突いた。
ゴツン!という、鈍い、しかし致命的な音。
マリは口から血を吐き出し、目を見開いた。彼女の冷酷な知性は、この結末を計算できなかった。彼女の視線は、倒れたケンの遺体と、ガラス片が刺さったサトウの腹部をさまよった。
サトウは、腹部の激痛に耐えながら、マリの身体を強く抱きしめた。
「これで……永遠に……私のものだ……」彼の声は、歓喜と苦痛で震えていた。
マリは、自分の胸元に食い込んだ鉄パイプの感触を感じながら、抵抗する力を失った。彼女の目から、光が消える。
マリとサトウは、互いに深く傷つけ合ったまま、瓦礫の上に抱き合うように倒れ込んだ。
彼らが最後に残したのは、血だまり、鉄パイプ、ガラス片、そして、二人分の遺体。
路地の影では、頭を打って気絶していたヤマモトが、その激しい争いの音と、絶叫を聞きながら、ゆっくりと意識を取り戻しつつあった。
彼は、眼鏡のないぼやけた視界で、二つの動かない人影を見つめた。
この廃墟の街に、生き残っているのは、ヤマモト、ただ一人となった。
「最後の一人に、救済を」。
ヤマモトは、死と裏切りが支配する地獄の中で、救済を手に入れた。
ヤマモトは、茫然自失のまま、目の前の光景を認識していた。
冷たくなったマリと、腹部から血を流して絶命したサトウ。自分の周りに横たわる三つの動かない人影。眼鏡がないため、すべてがぼやけているが、それが紛れもない勝利の証拠だと理解した。
彼は、荒い呼吸を繰り返す。この街で、生き残ったのは自分だけ。マリの冷酷な知性、サトウの倒錯した愛、ケンの傲慢な暴力。すべてが自滅した結果、彼は「救済」を手に入れたのだ。
「……救済」彼は掠れた声で呟いた。その声には、歓喜も、悲しみもなかった。ただ、空虚な勝利感だけが残った。
その瞬間、路地の廃墟全体が、信じられないほどの強い光に包まれた。
それは、太陽光ではない。上空から降り注ぐ、部屋全体を白く塗り潰すような、轟音と共に現れた人工的な光だ。頭上から圧力がかかり、地面全体が激しく揺れ動く。
山本は再び激しい吐き気と頭痛に襲われた。身体は光の中に溶けていくような感覚に囚われる。
「う、あ……!」
彼は光に抗えず、その白い閃光の中で、再び意識を失った。
次に目を覚ましたのは、冷たいコンクリートの上だった。
頭痛は消えていた。喉の渇きと、全身の冷たさ。天井にはシミがあり、カビと埃が混ざったような悪臭が鼻につく。
ここは、六畳ほどの汚い部屋。
ヤマモトは、身体を起こした。彼の目の前には、見覚えのある五人の男女が、意識を失っていたかのように床に転がっている。
彼らは、全員が混乱と恐怖に顔を歪ませながら、次々と覚醒し始めている。
「な、何が起こったのよ……」一人の女が、怯えた声で呻いた。
「わからん……最後に何をしていたかも、思い出せん……」老けた男が、額を押さえながら呻く。
ヤマモトは、その光景を、奇妙な既視感と共に見ていた。彼はもう、戸惑うことはない。すべてを経験した、ただ一人の生存者として。
その時、一人の男が、ポケットから白い紙切れを取り出した。そして、混乱した目で、山本に話しかけた。
「あ、あんた何か知らないか? 目を覚ましたらここにいて……ポケットによくわからない紙切れが入ってるんだが」
男の手に握られた白い紙片。山本は、その紙がどんなに多くの血と裏切りを伴うかを知っていた。
ヤマモトは、虚ろな目で、床に転がる五人の顔を見つめた。彼らは皆、ゴトウであり、ケンであり、マリであり、サトウだ。そして、タケダであり、過去のヤマモト自身でもある。
「最後の一人に、救済を」
ヤマモトは、冷たい床に手をつき、掠れた声で呟いた。
「…………あと、何人いるというのだ」